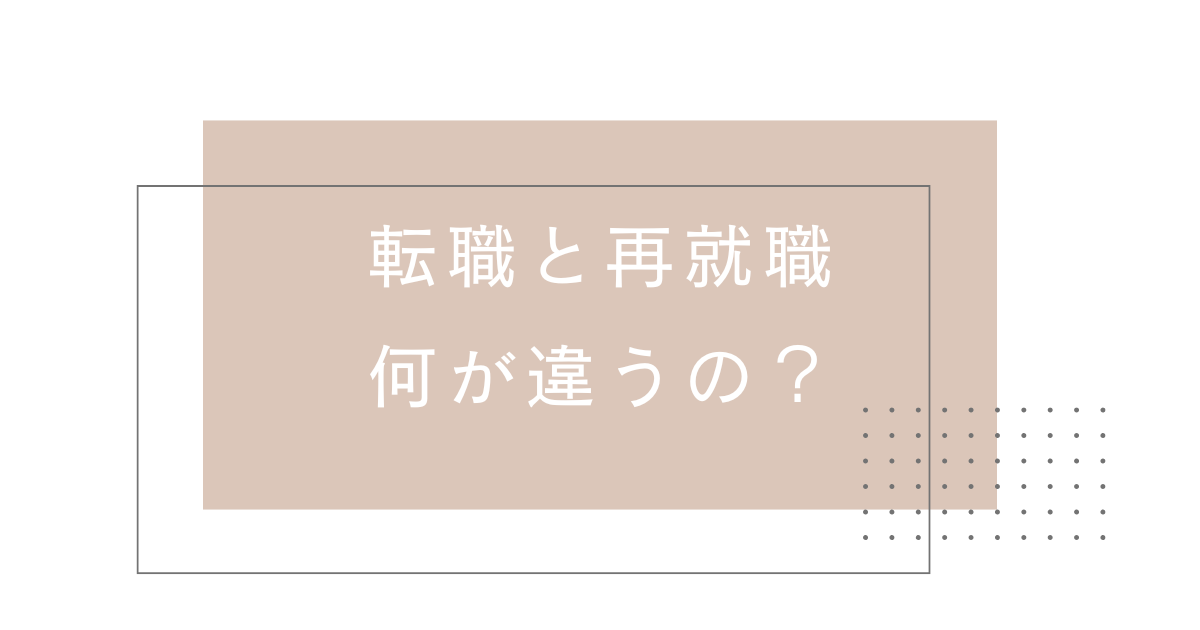「転職と再就職ってどう違うの?」
「今の自分は転職と再就職、どっちを選ぶべきなんだろう?」
この記事では次のことがわかります。
- 転職と再就職の定義や違い
- 転職と再就職、それぞれのメリットとデメリット
- 転職や再就職を考えるにあたって活用できるサービスや制度
結論からお伝えすると、「転職」は今の仕事から次の仕事へ期間を空けずに移ること、「再就職」は退職した後に生活や働き方を見直しながら新しい職場を探すことです。
この記事を読むことで、自分がどちらを選ぶべきかが明確になります。加えて、支援サービスや制度も理解できるため、効率的に次の一歩を踏み出せます。
迷いや不安を減らし、前向きに転職・再就職に向けた活動を行うために、ぜひ最後まで読んでみてください。
転職と再就職の定義と違い
転職と再就職は、どちらも新しい職場で働き始めるという点は同じですが、スタートの状況が異なります。
転職とは
転職とは、期間を空けずに現在働いている企業から別の企業へ移ることです。
キャリアアップや収入条件の改善を目的とする場合もあります。
例えば、営業職から企画職へ職種を変えるケースや、同じ職種でもより待遇の良い会社に移るケースが挙げられます。
転職は、今までの職務経験やスキルをすぐに活かせる一方、現職での業務と転職活動を並行する必要があるため、体力的・精神的な負担がかかることも。
再就職とは
再就職とは、前の職場を退職した後に、期間を空けて次の職場に就職することです。離職の理由は、出産や育児、介護、病気療養、留学などさまざまです。
仕事から離れていた分、前職と同じ職種に就きたい場合も、スキルや知識の学び直しが必要となることがあります。例えば、IT業界の仕事に戻る場合、新しいソフトやプログラムの知識を身につける必要があります。
再就職は、失業手当や再就職手当など、公的支援を利用できる点も特徴です。
転職・再就職の違いは?
転職と再就職は、どちらも新しい仕事を始めること。
しかし、状況や進め方が異なります。
以下の表に、違いをまとめました。
| 転職 | 再就職 | |
|---|---|---|
| 出発点 | 在職中 | 離職後 |
| 主な目的 | キャリアアップ 雇用条件の改善 | 生活や働き方の見直し 社会復帰 |
| 活動期間 | 在職中に短期間で進める場合が多い | ブランク期間を含み長期になる場合がある |
転職はキャリアを継続でき、再就職は生活や働き方を見直し新たなキャリアを始めるきっかけになります。
厚生労働省のデータから見る雇用状況
厚生労働省「令和5年雇用動向調査結果の概況」によると、2023年の入職率(※)は16.4%、離職率(※)は15.4%でした。
入職率が離職率を上回っているので、新たに働き始める人が少し多い状況です。
雇用動向調査は、全国の幅広い業種を対象に1年間の動きをまとめた結果なので、全体の雇用の流れをつかむ手がかりになります。
雇用状況の特徴と傾向:業種別
雇用動向調査では、業種ごとの入職・離職の動きも分かります。
業種別に見ると、入職や離職の動きが多いのは「宿泊業・飲食サービス業」「卸売業・小売業」「医療・福祉」です。1年で約20%ほど、人の入れ替わりがあります。
こうした業界は、転職や再就職のチャンスも比較的見つけやすい傾向があります。
雇用状況の特徴と傾向:年代別
年代によって入職・離職の動きには大きな差があります。また、男女ともに、入職者が離職者を上回る「入職超過」の状態にあります。
20代前半(特に新卒層)は入職率が最も高く、毎年多くの人が新しく職場に入っています。一方で、離職率も相対的に高く、就職後早い段階で別の仕事に移る人も少なくありません。
30〜40代になると、入職率・離職率はともに下がり、安定的に働き続ける割合が高まります。この年代では、キャリアアップや生活環境の変化による転職が主な理由になります。
50代以降では入職率がさらに低下し、離職率の方がやや高くなる傾向があります。定年延長や再雇用制度を活用して働き続ける人もいる一方で、体力面や家庭の事情から労働市場から離れる人も増えます。
こうした年代別の特徴を踏まえると、若年層は経験を積むための転職や新しい分野への挑戦、中高年層は安定性や働きやすさを重視している傾向があります。
年齢や働き方によって、求人の見つけやすさや選び方が変わるため、自分の状況に合わせて活動の計画を立てることがポイントです。
転職のメリット
転職には、働く環境や将来の可能性を広げるチャンスがあります。現在の職場で感じている課題を解決できるだけでなく、自分の能力や経験をより高く評価してもらえる職場に出会えることも。
転職には、次のようなメリットがあります。
- 収入アップや労働条件の改善を狙いやすい
- キャリアが途切れず安心
- 人脈や業務知識を活かせる
- 精神的負担が少ない
こうしたポイントを理解しておくと、転職活動の方向性がより明確になります。
それぞれのメリットについて詳しく見ていきましょう。
収入アップや労働条件の改善を狙いやすい
転職は、収入や働く条件を見直す大きなきっかけになります。今までの経験やスキルが評価されれば、前より高い給与や好条件で採用してもらえることもあります。特に同じ業種や似た職種の場合、スタートから即戦力として期待されることが多いです。
例えば、同じ営業職でも、成果に応じてボーナスが増える会社へ移れば、年収が大きく伸びることがあります。
待遇を上げたいときは、自分の強みや市場での価値を事前に把握しておくと安心です。
キャリアが途切れず安心
転職は、新しい環境に移りながらもキャリアが途切れずに成長できる手段です。これまで積み上げた経験を土台に、役職や仕事内容のステップアップを目指せます。
同じ業界の別企業へ移った場合、業務の流れや専門知識をそのまま活かせます。そこに転職先で身についた新しいスキルや経験が加わり、より幅広い役割を担えるようになることもあります。
これまでの道のりを無駄にせず、次の職場でさらに伸ばせるのは、転職の大きな魅力です。
人脈や業務知識を活かせる
転職によって、これまで築いてきた人脈や業務知識を新たな職場で活用できます。特に同業種や関連分野であれば、取引先や業界内のネットワークが仕事の成果に直結します。
人脈や知識は時間をかけて形成される貴重な資産です。自分の強みをさらに発揮できる環境づくりにつながります。
精神的負担が少ない
人間関係や残業の多さで精神的に参ってしまい、転職を考える人も多いです。仕事内容や働き方が自分に合っていれば、日々のストレスが減り、仕事への意欲も高まります。
転職で精神的な余裕ができることで、長期的に働き続けやすい環境を手に入れられます。
転職のデメリット
転職には新しい可能性がありますが、その一方で負担やリスクが伴うことも。日々の業務と並行して転職活動を進めるため、想像以上に時間やエネルギーを使う場面もあります。また、判断の仕方によっては長期的に見て不利になる場合も。
転職のデメリットには、次のようなものがあります。
- 時間の確保が難しい
- 十分な休養やリセット期間がない
- 短期的な条件だけで判断しがちになる
順番に見ていきましょう。
時間の確保が難しい
転職活動は、履歴書作成や面接準備など、多くの時間を必要とします。働きながら進める場合、平日の夜や休日に作業を詰め込みがちになり、休息や私生活の時間が減ります。さらに、面接が平日昼間に設定されることも多く、今の職場で有給を取らざるを得ない場面も出てきます。
例えば、1週間のうち3日を面接や企業研究に使えば、趣味や家族との時間は大きく削られます。体力的にも精神的にも負担が増えるため、スケジュールの管理が欠かせません。
限られた時間で動くからこそ、スケジュール管理をしっかりと行い、優先順位を決めながら効率よく進める意識が必要です。
十分な休養やリセット期間がない
次の職場で働き始めるまでの間に十分な休養を取れないことがあります。退職日と入社日が近いと、心身の切り替えが不十分なまま新しい環境に入ることになり、慣れるまでに余計なストレスを抱えることもあります。
h3:転職することを社内で知られるリスクがある
転職活動をしていることが社内に知られると、人間関係や評価に影響が出る可能性があります。
活動はできるだけ目立たない形で進め、信頼できる相手以外には話さない工夫が必要です。
短期的な条件だけで判断しがちになる
転職活動では、早く転職先を決めたい気持ちが強くなり、給与額や福利厚生など、目先の良い情報だけで応募先を選んでしまうことがあります。特に現職での不満が大きい場合、「とにかく早く辞めたい」と焦ってしまうため、注意が必要です。
求人を選ぶ際には、家族や信頼できる友人など、第三者の視点からアドバイスをもらうことも検討しましょう。
再就職のメリット
再就職には新しい環境で挑戦できるだけでなく、自分の生活や働き方を見直す良い機会にもなります。退職後に一定の時間を持つことで、これまでの経験を整理し、スキルを磨く余裕が生まれます。
また、公的な支援制度を活用すれば、経済的な負担を軽くしながら次のキャリアを探せます。
再就職のメリットには、以下のようなものがあります。
- 次の仕事に向けた準備やスキルアップに時間を使える
- 生活や働き方を根本から見直せる
- 基本手当や再就職手当などの失業等給付を受けられる
順番に見ていきましょう。
次の仕事に向けた準備やスキルアップに時間を使える
再就職までの期間は、計画的に使えば自己成長の貴重な時間になります。現職中は忙しくて学びに時間を割けない人も多く、退職後なら資格取得や語学学習などに集中しやすくなります。
例えば、IT業界を目指す人がプログラミングスクールに通い、実務で使えるスキルを身につけるケースがあります。1日2〜3時間を勉強に充てることで、数か月後にはポートフォリオを完成させられるでしょう。
準備期間を有効に使えば、面接でも自信を持って自己PRでき、採用担当者への印象も良くなります。
生活や働き方を根本から見直せる
再就職のタイミングは、生活リズムや働き方のスタイルを根本的に変えるきっかけになります。勤務時間、通勤時間、休日の使い方など、日常の要素を見直すことで心身のバランスを整えやすくなります。
例えば、長時間通勤に疲れていた人が、地元の企業やリモート勤務を選ぶことで、家族との時間や趣味の時間が増える場合があります。
環境を変えるだけでなく、価値観に合った働き方を選び直すことで、長期的なキャリアの満足度も高まります。
基本手当や再就職手当などの失業等給付を受けられる
退職後は、一定の条件を満たせば失業給付や再就職手当といった公的支援を受けられます。これらの制度は、生活費を補いながら落ち着いて次の職を探すための大きな助けになります。
例えば、ハローワークでの求職申込みや定期的な活動報告を行えば、給付金が支給されます。早期に再就職が決まれば、再就職手当を受け取れる場合もあります。
制度を活用すれば、焦って条件の合わない職に飛びつくリスクを減らし、自分に合った再就職先を選びやすくなります。
再就職のデメリット
再就職は新しい環境に挑戦できる一方で、いくつかの不利な点も考えられます。特に、職務経験に空白期間ができることで選考に影響したり、収入が途切れて生活に負担がかかることがあります。また、希望条件に合う求人が少ないケースもあります。
再就職のデメリットには、以下のようなものがあります。
- ブランクが評価に影響する可能性
- 収入の空白期間が生じる
- 求人の選択肢が限られる場合がある
順番に説明していきましょう。
ブランクが選考に影響する可能性がある
再就職では、退職から次の職に就くまでの期間が長いと、その理由や期間の過ごし方について面接で聞かれることがあります。
そのため、ブランクが開いた理由を具体的かつ前向きに説明できるよう準備しておくことが重要です。資格取得や研修受講、家庭の事情など、期間中の活動を整理しておきましょう。過ごし方次第で、ブランクは不利な印象を和らげることができます。
収入の空白期間が生じる
退職から再就職までの間は給与収入がないため、生活費や固定費の支払いが家計に負担となります。
失業給付を受けられる場合も、これまで得ていた給与額より低くなるため、支出の見直しが必要です。
例えば、家賃や住宅ローン、光熱費、保険料といった固定費に加え、食費や交通費なども継続して発生します。
収入の減少を見越して、退職前に数か月分の生活費を確保しておくと安心でしょう。
業種や職種の選び方
再就職や転職を考えるとき、最初に決めたいのが業種や職種です。方向性があいまいなままでは、求人探しに時間がかかり、条件比較もしにくくなります。自分の経験や興味、将来のキャリアプランを踏まえて選ぶことが、納得できる職場探しの近道です。
検討する際は、次のような視点から考えると整理しやすくなります。
- 年齢・キャリアの状況で判断する
- スキル・資格の有無で判断する
この2つの視点をもとに、現実的で挑戦しがいのある選択肢を見つけていきましょう。
年齢・キャリアの状況で判断する
年齢やキャリアの段階は、適した業種や職種を決めるうえでの重要なポイントです。
若手は成長性や将来性を重視した業界に挑戦しやすく、中堅やベテランは即戦力として評価される分野で強みを発揮できるケースが多いです。
例えば、20代前半ならITやマーケティングなど、新しいスキルを吸収しやすい分野への挑戦がしやすいです。40代以降であれば、製造業の品質管理や営業マネジメントなど、これまでの経験を直接活かせる職種が選びやすくなります。
自分の年齢とこれまでの経歴を照らし合わせることで、採用されやすい業種・職種が明確になります。
スキル・資格の有無で判断する
スキルや資格の有無は、業種や職種を選ぶうえでの重要な基準です。
資格や専門知識があれば、その分野での即戦力として評価されやすくなります。例えば、簿記2級があれば経理や会計事務所、ITパスポートを持っていればシステム運用やITサポート職で有利です。
一方で、資格があっても実務未経験では応募できない求人や、資格よりも実務経験を重視する会社もあります。例えば、宅地建物取引士(宅建)の資格があっても、不動産業界での経験がない場合は即戦力として採用されにくいケースがあります。
資格がない場合は、研修制度やOJTが整った会社を選ぶと成長の機会が広がります。自分の資格と経験のバランスを見極め、採用条件と照らして選択しましょう。
転職・再就職するためのおすすめ支援サービス
転職や再就職をスムーズに進めるには、支援サービスの活用が有効です。独力で探すよりも、情報収集や書類準備、面接対策などのサポートを受けることで、希望条件に合う職場を見つけやすくなります。特に、経験やスキルに合わせて適切なサービスを選ぶことが重要です。
代表的な支援サービスには以下があります。
・民間の転職エージェント
・求人サイト
・ハローワーク
・地域の就職支援センター・ジョブカフェ
順番に内容を確認して、自分に合った支援サービスを見つけましょう。
民間の転職エージェント
民間の転職エージェントは、担当者が個別にサポートしてくれるサービスです。履歴書や職務経歴書の添削、面接対策、非公開求人の紹介などを受けられます。特に即戦力が求められる職種では、経験やスキルに合った求人を探しやすい利点があります。
例えば、IT・Web業界であれば「レバテックキャリア」、営業職や事務職なら「リクルートエージェント」や「doda」があります。これらのサービスでは、担当者が条件に合う企業を複数ピックアップし、面接日程の調整もしてくれます。応募書類の改善点を具体的に指摘してもらえるため、選考通過率の向上にもつながります。
民間エージェントを活用すると、自分の強みを最大限に活かせる求人に出会いやすくなります。
求人サイト
求人サイトは、自分のペースで求人情報を探せるサービスです。業種や勤務地、雇用形態などで検索でき、応募も直接行えます。情報が豊富で幅広く比較できるため、条件に合う仕事を効率よく見つけられます。
例えば、「マイナビ転職」や「リクナビNEXT」は全国の正社員求人が豊富で、詳細な検索条件で絞り込みが可能です。「エン転職」や「はたらいく」では地域密着型の求人が多く、地元で働きたい人に向いています。これらのサイトでは応募状況や面接日程をサイト上で管理でき、進捗を一目で把握できます。
求人サイトを使えば、希望条件に合った仕事を自分のペースで探しやすくなります。
ハローワーク
ハローワークは国が運営する就職支援窓口です。求人の紹介だけでなく、職業相談や面接練習、各種助成金や制度の情報も得られます。費用がかからない点が大きな特徴です。
例えば、退職後に失業手当を受けながら、就職相談や職業訓練の案内を受けることができます。地域密着型の求人も多いため、地元で働きたい場合に有利です。また、若年者向けや高齢者向けなど、条件に応じた相談窓口も用意されています。
ハローワークを利用すると、経済的負担を抑えながら幅広い求人情報を得られます。
地域の就職支援センター・ジョブカフェ
地域の就職支援センターやジョブカフェは、若年者や転職希望者を対象にしたサポート施設です。履歴書作成や面接指導、職業相談、セミナー参加など、多面的な支援を受けられます。
例えば、ジョブカフェでは、20代の若者向けにキャリア相談を受けながら、模擬面接や自己PR作成の指導をしてもらえます。地元企業の紹介や合同説明会も行われ、直接採用担当者と接触できる機会があります。
こうした地域拠点を活用すると、個別の指導と地元企業情報を組み合わせて効率的に就職活動を進められます。
再就職にあたり活用できる制度
再就職にあたっては、国や自治体が用意する制度を活用すると、スキル習得や収入の安定につながります。特に、仕事を探す期間中に利用できる制度は、学び直しや転職活動を支える大きな支援になります。
以下の制度を理解しておくと、効率よく再就職の準備を進めやすくなります。
・職業訓練
・基本手当・再就職手当などの失業等給付
具体的な制度内容を見ていきましょう。
職業訓練
職業訓練は、再就職を目指す人が新しいスキルや知識を身につけるための制度です。訓練には、公共職業訓練と求職者支援訓練があり、受講中は一定の手当が支給されます。
例えば、IT系のプログラミング講座、介護職の実務研修、事務職向けの簿記やパソコン講座などがあります。訓練期間中は専門講師による授業や演習を通して即戦力を身につけられます。
職業訓練を活用すると、未経験の分野でも準備ができ、採用面接でスキルを証明しやすくなります。
興味のある方は、ぜひ最寄りのハローワークで相談してみてください。
ちなみに、ハローワークインターネットサービスから実施しているコースを検索することもできます。
基本手当・再就職手当などの失業等給付
基本手当や再就職手当は、失業中の生活を支えつつ、再就職を促すための制度です。
基本手当は、所定の手続きを行った後、求職活動をしている間に支給され、再就職手当は早期に就職が決まった場合に受け取れます。
これらの制度を利用すると、収入面の不安を減らしながら転職活動を進められます。
よくある質問(FAQ)
転職や再就職を検討する際には、疑問や不安が多く生じます。採用や給付、求人の探し方など、日常的に相談される内容を整理して理解しておくと、準備や活動を効率よく進められます。以下では、ブランクや退職理由、再就職手当の受給条件など、実務に即したFAQを紹介します。事前に確認して、安心して転職活動を進めましょう。
退職理由や転職理由の上手な答え方は?
退職や転職理由は、前向きな表現に変えて伝えることがポイントです。たとえば、業務の幅を広げたい、専門性を高めたいという理由なら、意欲やスキル向上の姿勢として評価されます。逆に不満や批判を中心に話すと印象を悪くしやすいです。面接では、理由を簡潔にまとめ、次のキャリアでどう活かすかをセットで伝えると効果的です。
早めに転職先が決まった場合、再就職手当はもらえるの?
再就職手当は、失業給付を受けている期間中に早期に就職が決まった場合に支給されます。ただし条件があり、ハローワークでの手続きや給付日数の残りなどを確認する必要があります。例えば、受給資格を満たし、所定の手続きを行えば、給付の一部をまとめて受け取れます。申請は必ず就職前に相談し、手順を確認しましょう。
効率的に求人を探す方法は?
求人を効率よく探すには、自分の条件と目標を明確にし、複数の情報源を活用することが重要です。例えば、転職エージェントで非公開求人を紹介してもらい、求人サイトで条件を絞り込む、ハローワークで地域密着の案件を確認すると効果的です。検索条件やアラート機能を活用すると、時間を節約しつつ希望に合った求人を見つけやすくなります。
公務員は失業給付をもらえるの?
公務員は雇用保険に加入していないため、失業給付や再就職手当は対象外です。
ただし、失業給付に代わる仕組みとして、退職後の生活費を補う退職手当があります。退職手当は勤続年数や給与額に応じて支給され、長く勤務していれば受け取れる額は増えます。たとえば、20年勤務した場合と10年勤務した場合では支給額に差があります。
詳しくは所属する自治体や部署の担当者へ確認しましょう。
まとめ
「転職」と「再就職」の主な違いは、活動を開始するタイミングにあります。
それぞれの特徴を理解し、自分に合った選択をすることが重要です。
| 転職 | 再就職 | |
|---|---|---|
| 定義 | 現在の職場に在籍しながら、キャリアアップや条件改善を目指して次の仕事へ移ること。 | 一度職場を退職した後に、生活や働き方を見直しながら新しい仕事に就くこと。 |
| メリット | ・キャリアが途切れず、収入アップを狙いやすい ・現在の業務知識や人脈を直接活かせる ・経済的な空白期間がない | ・働き方や生活を根本から見直せる ・資格取得などスキルアップに集中できる ・失業給付などの公的支援を活用できる |
| デメリット | ・働きながらのため、活動時間の確保が難しい ・十分な休養がないまま次の仕事が始まる ・焦って短期的な条件で判断しがちになる | ・経歴上のブランクが選考に影響する場合がある ・収入のない空白期間が生じる ・求人の選択肢が限られる可能性がある |
このように、転職と再就職は目的や置かれている状況によってメリットが異なります。
表を参考に、ご自身の状況と照らし合わせ、どちらがより自分に合っているかを見極めるための判断材料としてご活用ください。
もし一人で判断に迷う場合は、転職エージェントのキャリア相談やハローワークの職業相談など、専門家のサポートを活用するのもおすすめです。この記事で解説したポイントを参考に、後悔のないキャリアチェンジを実現してください。